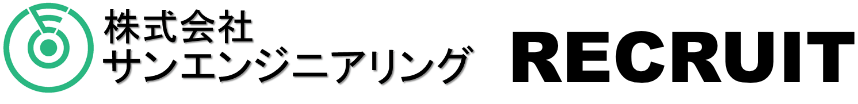about us 会社のご案内


代表ご挨拶

株式会社サンエンジ・東研究所
代表取締役 入戸野 義満
測量・点検分野で培ってきた
知見と技術を強みに
建設コンサルタントとして
新たな人材を育成し
これからの社会ニーズに
お応えしてまいります。
当社は、1992年に神奈川県藤沢市北部の測量会社として誕生しました。
以来30年以上にわたって地域の発展とともに着実に歩んでまいりましたが、近年、ビジネス環境の変化は、テクノロジーの進化に伴いますます大きくなっています。
測量の分野でいえば、トータルステーションによる測量に加え、3Dのレーザースキャナーやドローンを駆使した測量により、従来よりも高精度のアウトプットを短時間で出すことが可能になりました。今後、AIの活用により解析技術の高度化や人的作業の効率化はさらに加速していくものと思われます。
一方で、昭和の高度成長期に建設された道路、橋梁といったインフラは、半世紀の時を経て老朽化が進んでおり、今後もより安全に維持管理していくための対策が求められています。さらに近年では、大規模な自然災害によるインフラの崩壊や寸断といった被害も拡大する傾向にあり、防災の観点からも点検・調査のニーズが高まっています。
当社では、そうした時代の変化をしなやかに捉え、私たちの原点である測量分野に加え、点検・調査分野でも社会のお役に立つべく事業を展開してまいりました。2016年には建設コンサルタント登録を完了し、設計から施工管理へと、活動するフィールドを統合的に広げていきたいと考えています。
そのために最も重要となるのは、人であり組織です。当社ではこれまでも人材育成に力を注いでまいりましたが、先の読みにくい時代に向けて必要とされるのは、さまざまな局面において自ら考えて行動できる組織的なリーダーシップです。その実現に向けて当社では、働きやすい場の提供を中心に、人と人が自由に意見を交換し合い尊重し合い、ともに成長していかれる環境づくりに努めています。
持続可能な未来に向けて、社会インフラを整備するとともに維持管理していく私たちの仕事は、今後ますます重要になっていきます。まだまだ大きな会社ではありませんが、使命感をもって日々の業務に真摯に向き合いながら、新たな技術にチャレンジし、成長していきたいと考えています。
さらに2025 年には、設計分野で高い実績を持つ株式会社東建設研究所との合併を果たし、新たに「設計部」を設立いたしました。これにより、測量・調査から設計までを一貫して担える体制が整い、より総合的な技術提案が可能となりました。これからも地域社会の持続的な発展に貢献できる企業を目指し、挑戦を続けてまいります。
社是
・お客様のニーズに応えられる企業でありたい
・従業員に信頼される誠実な企業でありたい
・地域と共に歩み社会に貢献する企業でありたい
会社概要
-
商号
-
株式会社サンエンジ・東研究所
-
事業所一覧
-
本社
〒252-0801
TEL:0466-46-6213
神奈川県藤沢市長後678 丸屋本店ビル2FFAX:0466-46-6214
東京支店
〒194-0011
TEL:042-850-6623
東京都町田市成瀬が丘2丁目23-11 ワコービル成瀬 2FFAX:042-850-6624
-
資本金
-
1000万円
-
設立
-
平成4年11月 有限会社サンエンジニアリング
平成9年4月 株式会社サンエンジニアリングへ社名変更
令和7年7月 株式会社東建設研究所と合併
-
代表者
-
代表取締役 入戸野 義満
-
事業内容
-
測量・調査・設計・施工管理
-
登録
-
建設コンサルタント登録 建03 第10434号
-
測量業者登録
-
第(7)-21739号
-
取引銀行
-
りそな銀行 長後支店
横浜信用金庫 湘南台支店
かながわ信用金庫 長後支店
横浜銀行 長後支店
-
有資格者
-
技術士 技術士補
測量士 測量士補
二級土木施工管理技士 土地区画整理士
橋梁点検士
-
社員数
-
25名
アクセス
SDGs
藤沢市SDGs共創パートナー宣言書

わたしたちは、SDGsの達成に向けて取り組み、藤沢らしさを未来に引き継ぐことに貢献します。
当社は藤沢にて平成4年創業、インフラ整備に欠かせない測量業務及び点検調査業務によるサービス提供をして参りました。これからも地図情報や維持管理図⾯の作成、さらには災害復旧に寄与する測量を通じて地域に貢献し続ける所存です。インフラの⽼朽化問題について、点検調査という形でインフラメンテナンスの一翼を担います。
-

-
長時間労働や業務過多にならないよう人員を調整し、労働環境の改善に取り組みます。一人一人の生産性を評価し、技術力向上の奨励やドローンや3Dスキャナ(測量)、ロボットカメラ(橋梁点検)などの新技術も積極的に取り組んでいきます。
-

-
一人一人に合わせた教育体制と実務指導で、未経験者でも一人前の技術者になるまで丁寧にサポートします。資格取得にも積極的に支援し、性別や年齢や経験関係なく、誰もが技術を習得できる環境を整えます。また、現場作業での事故等を防ぐため、安全対策ルールを整備し、社員の安全教育研修を行うほか、安全パトロールや安全大会を実施します。また、定期的な面談を実施し、個々の状況に応じた職場環境改善を行い、従業員の心と体の健康を守ります。
-

-
社内における資料のペーパーレス化を進めます。
使い捨てプラスチックの使用を控え、ゴミの分別を徹底します。